2025/03/12/07. 勤怠管理の運用
「産休」とは?期間・対象者・給与・手当など運用上のポイントを解説

はじめに
皆さん「産休」という言葉は耳にしたことがあると思いますが、内容は良く分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、産休とはどのような制度なのかを簡単に説明した上で、産休の対象者・期間・給与・手当など、運用で留意すべきポイントを解説します。
「産休」とは?
産休は、正式には「産前産後休業」のことで、出産前と出産後の2種類のお休みがあります。産前産後休業は、労働基準法によって定められている休業であり、すべての会社で運用する必要があります。
産前産後休業に関連する法律や規定、「産前産後休暇」ではなく「産前産後休業」である理由について気になった方は、弊社別サイトの以下ブログ記事でもまとめていますので、参考にしてください。
産休は産前産後休業?産前産後休暇? ❘ コラム ❘ 大企業シェアNo.1勤怠管理システム「キンタイミライ」
対象者は?いつからいつまで取れる?
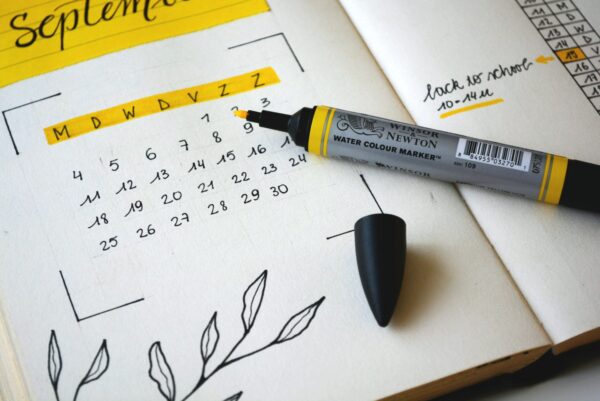
産休は、パート・アルバイト、契約社員などの雇用形態や、勤続年数に関わらず、出産予定があるすべての女性が取得可能です。
いつからいつまでの期間がお休みかは、産前と産後で異なります。
産前は、従業員から会社に請求することで出産予定日を含む6週間前(多胎妊娠は14週間前)から休業が可能です。
産後は、従業員の申し出に関わらず、原則8週間は就業させることが禁止されています。ただし、6週間経過後については、従業員本人が請求し、医師が認めた場合のみ就業が可能です。
産前は本人が望めば働くことが可能ですが、産後は本人の意思に関わらず必ずお休みする必要があります。
産休中の給料はどうなる?手当・社会保険料は?

産休期間中の給与は、会社にもよりますが基本的には無給です。
ただし、加入している健康保険に勤務者が申請することで、出産費用として1児当たり約50万円が支給される「出産育児一時金」や、産前産後休業期間の給料のおよそ2/3が支給される「出産手当金」を受け取ることが可能です。
手当の詳しい内容や金額の計算方法、申請手続きについては、協会けんぽの下記のページが参考になりますので気になる方はご確認ください。
出産に関する給付 | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
また、産前産後休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、会社が事務センターまたは管轄の年金事務所等へ申し出ることで、従業員と会社の双方で免除が可能です。
詳しい内容や、手続きの方法については、日本年金機構の下記ページが参考になりますので、気になる方はご確認ください。
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き
まとめ
産前産後休業は、労働基準法で定められており、すべての会社で運用する必要があります。
雇用形態や勤務年数に関わらず、出産予定のすべての女性が対象です。
産前は本人の申請に基づき、出産予定日を含む6週間前から休業が可能で、産後は本人の希望に関わらず、原則8週間(産後6週間経過後は例外あり)は就業が禁止されています。
産前産後休業中の給与は基本無給ですが、出産育児一時金・出産手当の給付や、社会保険料の免除の申請が可能です。
勤怠管理を行う上では、給与計算、賞与・年次有給休暇の算定等のために、休業期間の記録を行っておけると良いです。
弊社の勤怠管理システム「タブレット タイムレコーダー」では、下記のような追加項目を設定することで産休を登録することが可能です。
・追加項目1
利用する:ONにする
名称:産休
入力タイプ:チェックボックス
追加項目の詳しい設定方法については、下記のブログ記事からご確認ください。
【集計ルール設定】追加項目を設定する
こちらの記事もおすすめです
(最終更新日:2025/04/22 おすすめ記事追加)


